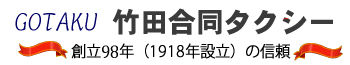![]()
西暦1185年、緒方三郎惟栄(おがたさぶろうこれよし)が源義経を迎えるため、 陣を置いたのが、始めとされています。1185年と言いますと下関の壇ノ浦で源平合戦が行われた時です。 戦には勝った義経でしたが、合戦のやり方で兄頼朝(よりとも)の怒りを受け、都を追われる立場となりました。 それを知った緒方三郎惟栄は、義経に九州に来るよう、手紙を出しました。 早速、瀬戸内海を船で、航行中大物浦の沖で難破し、本州に戻り逃避行が続きます。 緒方三郎惟栄は源義経をかくまうよう、画策した罪を受け、群馬県に流されました。
それから145年たち、大友の士族である志賀貞朝が館を造り、次第に増築を重ねて、 岡藩を興し、居城を岡城と命名しました。志賀氏は17代255年続きました。 1594年、中川秀成侯が兵庫県三木市から、岡城へ入場。 13代を経て廃藩置県の明治4年まで、277年続いた。 岡城の約700年の歴史の中で、一番の戦いといえば、志賀氏17代親次の時、 島津義弘の軍勢3万400の兵に対し、岡藩士1000名で城を護りきったことで、 難攻不落の城、日本三堅城の一つに数えられている。